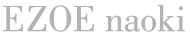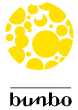tag:八百万の神
蔵書が溜まる。
2023.7.31好奇心が抑えられない。関心のあるテーマが夥しい。勢い深掘りしようとするわけだが、いまや情報源は誠に多様になった。オーソドックスな書籍を始め、電子図書、YOU TUBEなど、渇望を癒す文字や画像が簡単に手に入るありがたき時代。しかし、追い付かない。
百日紅の夏。
2023.7.25夏が盛りを迎えると、あちこちに白や紅、ピンクの花弁を房のように咲かせる百日紅。その名の通り、開花後もすぐに散り切ることもなく、長い期間咲き続ける。色の乏しい季節に、ホッとするような花木。日田のわが家にもシンボルツリーとして玄関脇に植えている。
螺旋的上昇。
2023.7.19あるいは螺旋的下降。豊かさと言われる暮らしの中身の話である。恐らく歴史の年表のせいだと思うのだが、太古の昔から現在に至るまで、ずっと直線的に進歩し、豊かになってきたと思いがちだ。僕は以前から、この感覚に違和感がある。本当に進んでいるのか?
普遍で本質。
2023.6.23身上らしきものがあるとすれば、染まらないこと。と答える。人にも、土地にも、組織にも、時代にも染まらず、常に自分自身を保っていたいと強く思っている。刺激を受けることはあるだろう。一時的に影響を受けることもないとは言わない。しかし、しかしである。
遊びの先に。
2023.6.6遊びをせんとや生まれけむ。のフレーズがあったのは、梁塵秘抄だったか。僕を含めて、わが遊びの肯定にしばしば引き合いに出される。編纂したとされる後白河院の真意はともかく、言い訳ではなく遊びの意義については、いまも変わらず強弁したくなることがある。
原石のまま。
2023.5.31あと2年半ほどで古希を迎える。ここへ至って初めて得る資格というものがあるような気がしている。つまり、過去を振り返る資格。昔話に埋没するのは、未来の見えなくなった老人の哀れだが、経験の中から普遍や原則を紡ぎ出すのも老人ならではの責務かと思われる。
発言しない。
2023.5.13すべき発言をしない方が多過ぎる。と直接的であからさまな指摘から入ったのは、それほど日常的に首を傾げているからだ。意見が無いわけではない、会議後の雑談では本音が出たりする。この傾向は、日本人の特質とも永く言われてきたが、もはやシャイでは片付くまい。
花を拾う。
2023.5.1毎朝散歩をする。田舎町のはずれ、大きな神社の鎮守の杜を、写真を撮りながらフラフラ歩いている。深山幽谷とまではいかないけれど、四季の変化は驚くほど多彩を極める。時は朝に限るものの、花鳥風月の豊かさに日々胸をときめかせている。中でも花は、饒舌だ。
シジミと土木。
2023.4.25もうひと月もすれば、近辺にはホタルが飛び始める。決して僕の住む場所は山奥ではないし、近くを流れるのは人工的な溝や疎水なのだが、ホタルにとどまらず、サワガニもハヤもシジミも生息する。ただ、どれも古い構築物で近代の無機質さとはどこか異なっている。
来た船に乗る。
2023.4.13あなたは、決してやって来ない船を延々と待っているかも知れない。どこにも存在していない船を。それを求めてやり過ごしているうちに、持ち時間は減り、いつの間にか世の中はまったく様相を変えている。次の場面でもまた、永遠に来ない船を待ち続けるのだろうか?
山の女と。
2023.4.7山女と書いて、ヤマメと読む。最初に出会ったのが、24歳の春だから、もう随分長い付き合いだ。最初の一匹は、大分県のY川源流で毛鉤に掛かった15センチほどの個体。僕はそれを両の掌に乗せ、河原にひざまずいてしばらく見入ったことを、いまも鮮やかに思い出す。
熾火を残す。
2023.4.1新しいプロジェクトは、突然始まるわけではない。時を遡っていくと、何年も前に思いついたアイデアを、アタマの中で転がし、発酵が進むと、まず親しい人に打ち明ける。反応を見ながら、さらに整理をしたり、表現を再考したり。それを何度も何度も繰り返している。
考えたくない。
2023.3.8これとほぼ同義で、「決めたくない」というのもある。前者が思考放棄なら、こちらは決断放棄だ。どちらもジワジワと自らの首を絞める。誰しもしんどいことはイヤだから、後回しや敬遠をしがちなのだが、状況は確実に追い込まれていく。これはもう間違いない。
似非について。
2023.3.2エセと読む。本物があって、偽物がある。これはわかりやすい。厄介なのは似非だ。似非とは本物に見せようとする偽物のこと。本物を気取る偽物は、無邪気に世を惑わす。恐らくそこには悪意はなくて、自分を本物だと信じたい天真爛漫こそが諸悪の根源なのだ。
歌に救われる。
2023.2.24人はなぜ歌を唄うのか。詞を編み、曲を奏で、なぜ声に出して唄うんだろう?喋りや記述とは異なる歌。朗読ではなく、旋律とリズムに託す想いの丈。それが他人に響き、場と時を超えて歌い継がれる連鎖。改めて考えると、なんとも不思議な営みではなかろうか。