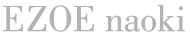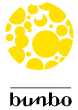tag:デザイン
フラー先生。
2024.5.8言わずと知れたこの御方。リチャード・バックミンスター・フラー。御名前は随分前から存じ上げているが、ドキュメンタリーは時々観るものの、御本を読んだことはなかった。それが、たまたま知人が翻訳している著作が目に留まり購入。初めてページをめくった。
正月準備。
2023.12.30今度の正月は、生まれて初めてひとりで過ごす。妻子はそれぞれの夢を追い東京にいる。家族で暮らしている頃は、暮れが押し迫ると、注連縄を飾り、いつの間にかお節ができ、大晦日には年越しそばも出てきたが、今年は随分地味で静かな年末年始になりそうだ。
プロモに堕する。
2023.11.27ブランディングという考え方が広まって、もうしばらく経つ。全国各地の自治体にも、ブランド推進課といった地域のブランディングを掲げたセクションが生まれた。僕自身も言葉としてのブランディングは、比較的使う。もちろん、流行に乗りたいわけでは決してない。
ロジカル。
2023.10.31タイトルを「思考の整理」にするか迷った。まあ伝えたいことはほぼ同じ。プロデュースに関するレクチャーなんぞをしていると、たまに「なぜ、それを良いと思ったのか?」とか、「自身のアイデアに迷いはなかったのか?」といった問いを投げられることがある。
リセット力。
2023.10.1910年近くジョグを続けていて思うことがある。オリンピックに出るようなトップランナーたちは、同じ人間とは思えない異次元のレベルで、僕のような凡庸なジョガーを驚かすが、いったい何が優れているんだろうか。最近なんとなくわかってきた。それは回復力。
関係を作る。
2023.9.19この世はすべて、目に見えるものと見えないものでできている。前者を具象と言い、後者を抽象という。見えるものだけでそれらを解釈し、説明しようとすると、表層をなぞらざるを得ず、当然本質から遠ざかることになる。ありとあらゆるものにこの構図は付いて回る。
抽象的仕事。
2023.9.7プロデュース。わかりづらい仕事のようだ。チームスポーツの監督に喩えたり、オーケストラの指揮者になぞらえたりするが、そこで膝を打つ人はそんなにいない。過去の実績を知って、ボンヤリ納得していただくことが最も多いだろうか。見えるのはそこだけだから。
教室にて。
2023.6.18長く教えているデザイン専門学校の授業は、雑談余談を重視している。柱は、いくつかのテーマに沿った僕の仕事のケーススタディなのだが、切りが悪く間が空いたりすると、迷わずそんな時間になる。入り口は枠をはめない質疑応答。なんでもありというのがポイントだ。
白色光。
2023.5.19リビングの間接照明が切れて、取り敢えずストックがあったLEDに換えた。蛍光色だったので、光が当たる漆喰壁は白けて見えた。明日にでも電球色の球を買いに行こう。そう思わせる嫌悪感がこころに滲む。突然、僕はかつてこんな気分を友に伝えたことを思い出した。
政治家こそ。
2023.4.19いつの間にかプロデュースが生業になった。全体計画の統括者。最初から、すべてに関われる仕事。そう思ったので、大変なことも覚悟しながら、もう30年近くこの仕事を続けている。もっとも、それまでのコピーライター以上に、皆さんへの説明が難儀この上ない。
熾火を残す。
2023.4.1新しいプロジェクトは、突然始まるわけではない。時を遡っていくと、何年も前に思いついたアイデアを、アタマの中で転がし、発酵が進むと、まず親しい人に打ち明ける。反応を見ながら、さらに整理をしたり、表現を再考したり。それを何度も何度も繰り返している。
名医たること。
2023.3.14この世のあらゆる仕事の目的が、課題の解決だとすれば、医者になぞらえるのがより自然な感じがする。症状の原因を突き止め、患部を探り当てる。静養、投薬、注射、手術といった治療法を決め、その処方箋を書き、施術後の経過を観察し、必要あらば善後策を練る。
答合わせ。
2023.2.6プロデューサーの最も大事な役割は、コンセプトとイメージの監修だと思っている。プロジェクトの背骨となるこのふたつを、ありとあらゆる伝え方を試みて、関係者に可能な限りシェアを図るのが、最初の大仕事だ。前者は編集方針、後者はビジョンに近いだろうか。
キャバノンの夢。
2023.1.25いつの頃からか、狭小住宅に憧れている。必要最小限の居住空間。茶室のような住まいと言った方が、ニュアンスはより正確だ。「行く川は絶えずして」の出だしで知られる鴨長明の方丈記。後半は方丈つまりわずか3m四方の庵を編み、そこで暮らす決意が述べられる。
野暮は大罪。
2022.10.29野暮をカジュアルに言うと、ダサい、かな? ダサいのって、良くないよね、という話。ファッションとかそういうのはまだいいとして、罪深いのは仕事を含む大事な局面でのダサいこと。野暮なこと。楽しさや美しさを後回しにする、余白の乏しさとでも言うべきか。