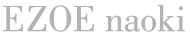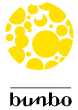tag:デザイン
視点の移動。
2022.6.27企業にしても自治体にしても、僕ら外部の人間がお手伝いするメリットは、その専門性よりも実は圧倒的に「客観性」だと考えている。組織内の皆さんとは違う視点を備えていることが、実は外部ブレーンの最大の存在意義なのではあるまいか。それほど客観視とは難しい。
実を摘みたければ。
2022.6.1もう20年以上前、自分のプロデュースをいかにわかりやすく説明するかに知恵を絞っていた頃、デザインツリーなる落書きをしたことがある。経営におけるコンセプトと戦略と戦術、そして最終利益との関係を拙いイラストにしたものだが、いまもなかなか重宝している。
お墨付き。
2022.5.5小社Bunboを立ち上げた25年前、広義の編集、プロデュースの可能性にひとり興奮して、ありとあらゆる方面に吹聴していたが、反応は冷ややかなものだった。精一杯理論立てて、言葉を選び、委を尽くして話したはずだったが、結果は連戦連敗。愕然悄然としたものだ。
反Excel 脳。
2022.4.29最初に断っておく。これから展開する珍説は、完全なる個人的偏見である。悪口に聞こえたとしたら、それは明らかに誤解であるし、どうしてもそうは思えないとなれば、単なるオヤジの妄言と、寛容なる御心にて爽やかに笑い飛ばしていただきたい。切にお願いする。
医者として。
2022.4.23僕の仕事は、全体を司るプロデュース業だが、さまざまな制作物が発生し、その監修つまりクリエイティブディレクションも、作業の主要を占める。まず、ヒアリングで事情を把握し、コンセプトワークという考えの整理を経て、なにをすべきかという判断に辿り着く。
ヤ生研のこと。
2022.2.27やせいけん、と読む。正式名称は、ヤブクグリ生活道具研究室。10年前に、林業振興を掲げて発足した任意団体ヤブクグリ。この名称は、拠点である大分県日田市の杉の固有種をそのまま屋号としたものだ。発足式は、市内を貫流する三隈川に筏を浮かべたりした。
応用、転用。
2022.2.13気づけば、もう長いこと「編集」と言い続けている。便宜上、プロデューサーを名乗っているが、本音は編集者だと思っている。ただし、広義のそれ。ページもののコンテンツの話なんかではない。まったくない。対象はあらゆる事象に及ぶ。ホントになにからなにまで。
総合編集。
2022.1.7プロデューサーを名乗っているが、心情的には編集者だ。ただし、広義の編集。などと言ってきた。著者と向き合い、本などを作る職能という意味の従来の編集者像から少し飛躍して、いやかなり飛躍して、より大きく複雑な要素を組み直す仕事。それがプロデュース。
産みの苦しみ?
2021.11.30なにか新しいことを始めようと画策するとき、基本的にモデルは探さない。アタマの中に広がる茫洋混沌としたアイデアを、必死で言葉やイメージに換えようと悶々とする。昨年から進めている西日本新聞社との取り組みが、今まさにそんな感じ。editforestってなんだよ?
要望に応える。
2021.9.7お客様の声に応える。良く耳にするフレーズだ。要望≒ニーズにしっかり応えることこそ仕事との論説は多い。ボンヤリ聞いてると頷きそうになるが、しばらく考えていると果たして本当かなと思い始める。クライアントの口からこぼれた言葉は、そのまま要望だろうか?
才能の使い途。
2021.9.1たまにTVCMを見て、決して多くはないが、面白いなあと感心することがある。コピー、デザイン、演出、企画。クリエイターの端くれとして、うまいなあと唸らされることがある。ただ、ふとその世界観が、缶コーヒーを売るためなのかと気づき、急に切なくなったり。
戦術の固定。
2021.5.7戦略と戦術。この違いを明確に自覚している人は、意外と少ないのかも知れない。何十年も、それが同じじゃなく、加えて戦略の重要性を説き続けた身としては、「誰もがわかっているわけではない」ことがわかっただけでも、時を経た意味はあったのかと思っている。
Howの蓄積。
2021.5.1近ごろ改めて、常識の功罪を考えている。大阪のプロデューサーとやっているYOU TUBEのテーマで「常識と非常識」の回があって、常識を自分なりに解析してみたりした。すると、また少し鮮明になったことがある。実は常識は役に立つ。いや本当。皮肉じゃなく。
editforest発進。
2021.4.3エディットフォレストと読む。和訳だと編集の杜。なんだそれ。まあ、そうだよね。そもそもの始まりは、九州経済産業局のデザイン系のプロジェクト。普通なら、クリエイターが集結するその場に、西日本新聞社が参加していた。それがすでに新しい萌芽だった。
手描き復活。
2021.3.17ずっと気になっていた。PCを触り始めてもう何年になるだろう?いつのまにやら作文は、ペンと原稿用紙ではなくて、キーボードとモニターの作業になってしまった。筆と和紙が、万年筆と洋紙に変わったような、いわゆる道具の変遷とは少し違う。いや、だいぶ違う。