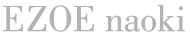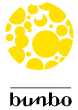tag:自然
一木一石。
2024.6.7木を見て森を見ず、とは、視野狭窄や全体観の欠落を戒める名言だが、これは部分と全体の因果関係の重要性を諭す至言でもある。森の一木が、その森の風のあり方を決め、川の一石がその川の流れを決める。1本の木の植え方、1個の石の置き方が与える影響について。
11年目のウサギ。
2024.6.1数日前の午後。いつもの尾根道をジョギングしていた。例によって、復路の上りを喘ぎながら走っていると、視界の左端に小さな動くもの。地を跳ねる鳥かと思ったが、挙動が少し違う。近づいていくと、なんと野ウサギだった。しかも子ども。ついに見つけた、と思った。
ホタル散歩。
2024.5.14GWが終わってしばらくすると、この時季ならではの愉しみが訪れる。ホタルだ。日田に越してくる前に住んでいた隣村では、山上に住まいがあったこともあり、周辺にはたくさんのホタルが飛んでいた。街に近くなる新居では、もう見られないかもと覚悟をしていた。
おふざけ老人。
2024.4.26今年も行ってきた。若葉萌える広葉樹の森。大分県庄内町にある男池湧水は、大人気スポットだが、実はその先に美しい森が広がっていて、僕らのお目当てはいつもこっち。春の新緑も素晴らしいし、秋の紅葉もこれまた感動的で、毎年時間をやりくりしては出掛けている。
釣り人の嘘。
2024.4.18釣れればたちまち有頂天になり、釣れなければ簡単に絶望してしまう釣り人の滑稽を、楽観的悲観主義者と喝破したのは、あの開高健だ。釣り人に話をさせるときは、両手を縛れとは、話す度にサイズが上がっていく彼らの無邪気を揶揄する、どこかの国の古い諺。
夜更けの咆哮。
2024.4.6現在のわが家は決して山奥にあるわけではないが、夜は充分に暗く静かになる。10軒ほどの家が点在するなだらかな傾斜を持つ小さな扇状地で、大原神社に繋がる逆V字型の森に囲まれている。思いの外動植物も多く、鳥はもちろん、蛍もいるし、キツネも見たことがある。
妖艶なるもの。
2024.3.31毎年繰り返し書いている話題はいくつかあるが、桜にまつわる想いもそのひとつ。花の中では最も好きで、その妖艶な美しさに陶然としながらも、移ろいの早さに背中を逆撫でされるごとくにソワソワとさせられ、散った後の花弁の絨毯や花筏の儚さについ悄然となる。
朝夕の色。
2024.3.19春はあけぼのと言ったのは、枕草子の清少納言だったか。これは、夏は夜。秋は夕暮れと続く。なるほどと頷くことも多いけれど、季節を問わず、僕は夜明けが一番好きで、次に夕暮れが来る。明暗が入れ替わるこの時間帯は、どこか不思議で特別な感情が付きまとう。
正月到来。
2024.3.11月1日は、世間の正月だが、ヤマメ釣り師にとっては、3月1日が正月である。前年の9月末日をもって禁漁となり、季節も冬に入る。そしてその冬が明ける弥生早春。ヤマメたちはもう動き出している。釣り人もまた、道具の埃を払い、ようやく年が明けるのだ。
無常について。
2024.2.6所詮一瞬だと思っている。いや、わが人生のことだ。薄っぺらい人生観の根底にそんな気分が確かに潜んでいる。それは今に始まったことではない。10代の終わりの混沌の中で、もがき苦しんだ挙げ句に掴んだ予感のような、諦観のようなもの。ただ、厭世感とは違う。
フジヤマ。
2023.12.12ふ〜じは、にっぽんいちのやま〜。富士山を見たことのない子供の頃から、この歌は知っている。大人になって、東京に行くようになり、時々飛行機の窓からチラリと見やる程度。それが数年前、縁あって麓の町富士吉田に何度か訪れたことがある。その巨大さに驚いた。
初冬の設え。
2023.12.6ブンボの打合せ室に入る表玄関は、普段の生活では使わないパブリックエントランス。何人かのお客様がいらしても、玄関で鮨詰めにならないようにゆったり作った。素材は三和土。下駄箱の上はちょとしたギャラリースペースで、オブジェが並び、壁には絵が掛かる。
江副の樹?
2023.11.12ここのえ低山部の、山の先輩たちに、そんな名前の木があると聞いたときは、もちろん冗談だと思った。いや本当にあったのだ。毎年、必ず春の新緑と秋の紅葉を楽しみに訪れる大分県庄内町男池。有名な湧水から少し歩いた先にこの木はある。見上げるほどの見事な大樹。
ムカゴに興ず。
2023.10.25もう毎年のこと。釣りが終わって、10月の声を聞く頃、あちこちで視界に入ってくる。細面のハート型の葉っぱが、急に目に付くようになって、どれどれ実は付いたか?とモードの転換が起こり、つまり秋が始まる。となると、俄然朝の散歩が楽しくなってくる。ムカゴ。
ドングリの音。
2023.10.7毎朝、境内へ通じる百段階段を上がる。そこは両側に大木が生い繁っていて、春夏秋冬さまざまな表情を見せる。春は若葉が萌え出し、夏は鬱蒼とした緑陰が涼を生み、秋は紅葉と落葉がはかなげで、冬は木々が葉を落とし切り、日射しが広がり意外にも明るくなる。