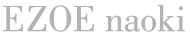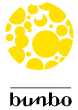tag:メディア
旧メディア凋落。
2023.9.13時代は変わる。刻々と、確実に。テクノロジーの進化は、そのめまぐるしさにおいて、驚愕の一途。かたや、人の営みは何万年も、それほど大きな変化はない。古今東西、食べて、働いて、子孫を残す。変わるものと変わらないもの。不易流行とはこのことだろう。
名医たること。
2023.3.14この世のあらゆる仕事の目的が、課題の解決だとすれば、医者になぞらえるのがより自然な感じがする。症状の原因を突き止め、患部を探り当てる。静養、投薬、注射、手術といった治療法を決め、その処方箋を書き、施術後の経過を観察し、必要あらば善後策を練る。
フローとストック。
2022.8.31日々表層を流れるものと、時折底に蓄積されていくもの。これは貨幣にも情報にも当てはまる。僕も含めて、人はついつい眼前のフローにかまけて、いつ役に立つかわからないストックをないがしろにしがちだ。でも、恐らく僕らの人生を豊かにするのは後者なのだ。
産みの苦しみ?
2021.11.30なにか新しいことを始めようと画策するとき、基本的にモデルは探さない。アタマの中に広がる茫洋混沌としたアイデアを、必死で言葉やイメージに換えようと悶々とする。昨年から進めている西日本新聞社との取り組みが、今まさにそんな感じ。editforestってなんだよ?
言葉が象る。
2021.8.6かたどる、と読む。いつの間にか、言葉を生業とするようになって、もう35年を超えた。コピーライター専業は、30歳から10数年だが、プロデュース業が主になってからも、企画やイメージの伝達は、自ずと言葉が先導し、プロジェクトの可視化と牽引を担っている。
SNSは鍋釜。
2021.7.25表現がいかにも古い。すっかり日常と言いたかったのだが。いや、SNSのことである。デジタルやネットといった新たなテクノロジーが、僕らの生活に入り込んでしばらく経つ。この新参インフラに、直接間接関わりなく生きている人は、いま果たして何人いるだろう?
言葉が沁みる。
2021.6.20さまざまな情報が溢れている。多様なメディアから、奔流のように押し寄せる夥しい言葉。僕らは、それを取捨選択しながら、日常や未来をかたちづくり、今日を生きている。そして、それらの言葉には、素直に受け取れるものと、そうじゃないものがある。
使わない言葉。
2021.3.28世にはいろんな言葉が行き交っている。文字離れなどと言われながら、その実こんなに人々が文章を書いている時代はない。それを加速させたのは、言わずと知れたSNS。糸井重里氏だったか、「いまの人は、読み過ぎ、書き過ぎ、調べ過ぎ」と喝破した。まったくもって。
手描き復活。
2021.3.17ずっと気になっていた。PCを触り始めてもう何年になるだろう?いつのまにやら作文は、ペンと原稿用紙ではなくて、キーボードとモニターの作業になってしまった。筆と和紙が、万年筆と洋紙に変わったような、いわゆる道具の変遷とは少し違う。いや、だいぶ違う。
っぽいこと。
2021.2.26世間の何かに対する違和感は、誰しも多少は持っているだろう。その対象はさまざまかもしれないが、僕もずっと胸の底に溜まっていたことがある。本編、原本ではない、要約版やダイジェストが大手を振る風潮とでも言うか。ほら、なかなかうまく言葉にできない。
読書は交際?
2020.9.14僕はずっと、読書は対話だと言ってきた。著者の言説を聞き、そうかあなたはそう考えるのか、翻って僕はどうだろうと自問自答を繰り返す。本の種類にもよるが、多くは著者の思想や世界観が露出するわけだから、結果そんな展開になる。対話は延々と続いている。
EZOESAKI
2020.9.3何かと縁の深い大阪で始まったふたつのトークイベントがある。そのひとつ、「クリエイティブは旅に出よ」は、異分野のゲストを招き、クリエイターに越境を勧める仕立て。もうひとつが、今回紹介するEZOESAKI。僕、江副直樹と、大阪のエサキヨシノリの掛け合いだ。
The Men’s Room
2020.5.25とてもいいドキュメンタリーだった。あまりに良かったので、録画を消せずにいる。繰り返して何度も見ている。普通を扱って、普遍に至る。理想的な仕事。いや、そんな野暮は言うまい。キミはあの感覚がわかるか? あれがわからないヤツとは友だちになりたくない。
御用聞き。
2020.5.13お客様の声というのがある。有権者の声もそれに近い。ニーズと言ったり。それを聞くための行為をヒアリングと呼んだり、リサーチもその類だろう。昔の日本語なら御用聞きだ。そしてこの御用聞きの有り様が、本質から外れる危険を想像以上に抱えているという話。
ふたつの旅。
2019.12.19最近関わっているふたつの出来事。クリエイティブは旅に出よ。たびするシューレ。どちらも旅がキーワードだ。前者は通称クリ旅。後者は、同じくシューレなどと呼んでいる。どちらもほぼ同時期に始まった。前者は大阪、後者は大分で開催されるトークイベント。