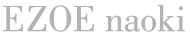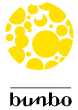tag:文化
美女と会食。
2024.7.14毎日更新しているFBやインスタに、しばしば美女との会食予定や、実際の写真をアップしている。顔はまず出さないから、見ているみなさんは、どれほどのなの美女か気になっているに違いない。特に野郎どもは。他の男がモテてるのは気になるし、なにより癪だからね。
鄙には希な。
2024.7.8ヒナニハマレナ、と読む。鄙とは田舎のことで、鄙には希な美人などという使い方をする。都会と田舎の格差が大きな時代において、田舎にしては、相対的にレベルの高いモノやコトに出会った際の、驚きの言い回しだ。田舎の三年より京の昼寝、などとも揶揄された。
公私の境目。
2024.7.2名ばかりだが、ブンボは株式会社である。しかし、オフィスは自宅の一部である。法人になる前から長くフリーランスなので、もう40年近く通勤をしていない。ブンボは一応週休2日である。しかし、曜日を問わず仕事をしている。公私の境目はないがごとくである。
運動不足。
2024.6.26今年の梅雨はよく降る。青空を見ることが珍しくなると、生活が変わる。日課の朝の散歩ができなくなり、週に数回のジョグも無理となり、この時季のメインプログラムである鮎釣りも行けなくなる。左手首のApple Watchが、運動負荷が激減していることを警告する。
伝える作法。
2024.6.20この世はすべてコミュニケーションだ。繰り返される膨大な意思疎通が、僕らの日々を作っている。家族で、地域で、仕事で、果ては外交で、多様で夥しいコミュニケーションを続けている。伝達、提案、交渉、説得と、その目的によって、精度と強さが変わってくる。
無手勝流。
2024.6.13独学について考えることがある。一般には、いわゆる正統な、体系立った知識やノウハウを学んで、人は新たなスキルを身に付ける。当初は、広大無辺なそもそもの対象への理解や、必要なスキルの修得のきっかけさえ見つからない。となれば勢い師匠を探すことになる。
一木一石。
2024.6.7木を見て森を見ず、とは、視野狭窄や全体観の欠落を戒める名言だが、これは部分と全体の因果関係の重要性を諭す至言でもある。森の一木が、その森の風のあり方を決め、川の一石がその川の流れを決める。1本の木の植え方、1個の石の置き方が与える影響について。
料理オヤジ。
2024.5.2010年近く前から、長男の市外進学などに絡んで、自炊をする機会が増えた。ヤツが卒業した後は、日田でしばらく次男とふたりで住んでいて、家事は当然僕の担当になった。そんな彼も昨春から東京で活動する母親と暮らし始めたので、以降完全なひとり暮らしである。
ホタル散歩。
2024.5.14GWが終わってしばらくすると、この時季ならではの愉しみが訪れる。ホタルだ。日田に越してくる前に住んでいた隣村では、山上に住まいがあったこともあり、周辺にはたくさんのホタルが飛んでいた。街に近くなる新居では、もう見られないかもと覚悟をしていた。
フラー先生。
2024.5.8言わずと知れたこの御方。リチャード・バックミンスター・フラー。御名前は随分前から存じ上げているが、ドキュメンタリーは時々観るものの、御本を読んだことはなかった。それが、たまたま知人が翻訳している著作が目に留まり購入。初めてページをめくった。
僕の中のDX。
2024.5.2名刺なんかに普通に書いてある、固定電話とFAX番号。僕も名刺にも、HPにも入れているが、いまどれくらいの人が使っているのか。そんなことを改めて考えたら、無性に不要な気分が募って来て、まずすぐに変えられるHPの記載を外すことにした。だって要らないもん。
釣り人の嘘。
2024.4.18釣れればたちまち有頂天になり、釣れなければ簡単に絶望してしまう釣り人の滑稽を、楽観的悲観主義者と喝破したのは、あの開高健だ。釣り人に話をさせるときは、両手を縛れとは、話す度にサイズが上がっていく彼らの無邪気を揶揄する、どこかの国の古い諺。
便利の度合い。
2024.4.12愛車smartがぶっ壊れた。その理由や回復の目処については、ここでは割愛することにして、お題はやって来た代車にまつわる喜劇について。どんな代車がやって来るかは、もう巡り合わせ。ディーラーに預けるときは、一生乗ることのない豪華なベンツが来たりする。
夜更けの咆哮。
2024.4.6現在のわが家は決して山奥にあるわけではないが、夜は充分に暗く静かになる。10軒ほどの家が点在するなだらかな傾斜を持つ小さな扇状地で、大原神社に繋がる逆V字型の森に囲まれている。思いの外動植物も多く、鳥はもちろん、蛍もいるし、キツネも見たことがある。
妖艶なるもの。
2024.3.31毎年繰り返し書いている話題はいくつかあるが、桜にまつわる想いもそのひとつ。花の中では最も好きで、その妖艶な美しさに陶然としながらも、移ろいの早さに背中を逆撫でされるごとくにソワソワとさせられ、散った後の花弁の絨毯や花筏の儚さについ悄然となる。