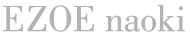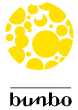tag:戦略
狩猟と農耕。
2021.4.9縄文と弥生とするのは、あまりに乱暴だろうから、基本的なライフスタイルで分けてみた。でも、伝えたいのは人のタイプ、性格の違い、生き様の差といったあたり。近ごろ、いろんな方々と仕事をしていて、こうした根本的な違和感に包まれることが度々ある。
芸能的情報群。
2020.8.23テレビの凋落が著しい。特に在京の民放。NHKは好番組も少なくないので、まったく同じではないが、タイトルの傾向と無関係とは言わない。さらにそれらを臆面もなくなぞるローカル局の惨状には今回は触れない。とまれ、問題は発信される情報の質についてである。
プロトタイプ。
2020.6.6雛型。あるいは、役割について。あるいは、向き不向きについて。もう20年以上、事業プロデュースなる仕事をしている。見えてくる課題に対して、基本ゼロから解決策を考える。方法における原則はあっても、ルーティンやマニュアルはない。勢い、毎回初体験になる。
前提を変える。
2020.5.31いい企画、いいアイデアには、共通の特徴がある。それは、必ず前提に踏み込んでいること。きっかけは、前提にこそある。一方、世に転がる数多の仕事は、繰り返し。先行する事例があり、それをなぞる。新しいと言っても、多くは所詮マイナーチェンジにとどまる。
ユーモア考。
2020.5.1辛いより楽しいほうがいい。泣くより笑うほうがいい。誰だってそうだと思うが、ただボンヤリと状況を期待しているのと、積極的にその空気を作りに行くのとでは、雲泥の差があると思っている。笑いは、自然発生するのではなく、自発的に産み出していくものだろう。
OSが違う?
2019.12.12わかっている。これを言ったら、もう敗北。とりつく島がない。意思疎通放棄。と言いたくなるくらい、コミュニケーションに難儀する相手がいる。それを言っちゃーおしめーよ、と諭してくれるのは寅さんだ。プロデュースは説得業と言っている身としてはこれはまずい。
見えてから。
2019.11.22何事も見えてから。結局ここなんだなと繰り返し気づかされる。ずっと前から言葉では伝えている。え、何度も言ったじゃないか、と思ってしまうが、聞かされた側としては何も像は結んでいなかったり。僕が思っているほど、周囲にビジュアルは付いてきていないのだ。
代案を出せ。
2019.9.21わかりやすくするために、こんなタイトルにした。会議が多い。無駄な会議はないつもりだが、コトは話し合いで進むからこれは必然と考える。そしてここに掟がある。否定だけをする虫のいい意見。粗探し、揚げ足取りは厳禁。建設的であってこそ会議は意味を成す。
毒を盛るように。
2019.8.19プロデュースは説得業だと言うことがある。新たなアイデアが出て、それを構想に膨らませようとするとき、関わる人が増えていくわけだが、共感が必ずしもスムースに広がらない局面が生まれてくる。理解の不足なら再度の説明を施し、感情のもつれなら飴と鞭を考える。
常識を脱ぐ。
2019.7.23常識に囚われてはいけない、などと言う。一方で、そんなの常識でしょ?とも言われることもある。常識から本気で自由になると不自由なことも多々。常識とは、生きていく上で覚えておくべき社会的なルールや作法でいながら、その中に住むと不便で退屈なことがある。
苦くない薬。
2019.3.22昔の諺、格言の類には、短く平易なフレーズで、見事に真理を言い表しているものが少なからずある。古今東西に通用し、この先も言い伝えられて、表現としても上質で、改めて見るたびに感心することしきり。今回のテーマの「良薬は口に苦し」もまさにそのひとつ。
説得の行方。
2019.1.25プロデュースは編集であるという定義に加えて、プロデュースは説得業だと言うことがある。プロジェクトの局面局面で、他人の意識に働きかけ、考えを修正していただき、逡巡する気持ちを覚悟に変えていただく瞬間が必ず訪れる。推進のための重要なプロセス。
不意の韓国へ。
2018.12.20扉はいつも突然に開く。ある日、某大学の先生からメールが届いた。曰く、淡路のプロジェクトについて書いた本の韓国語版が出ていて、それを読んだ韓国の方からレクチャーの打診があるという。以後は、直接連絡を取り合うようになった。日本語がご堪能で大助かり。
沈まない船。
2018.10.20これまで組織に所属したことは、1年強のサラリーマン生活のみ。以来、自由なような不自由なような、まあ気儘な人生。ただ、仕事でのお付き合いは組織のほうが断然多い。組織のなんたるかは、考えたくなくても考え続けるはめになる。良いところと悪いところ。
ルアー開発。
2018.10.7分野を特定しない仕事をしたくて、屋号をBunbo(分母)とした。これまで、多様な領域の分子とさまざまなプロジェクトを行ってきた。毎回ジャンルが違っても、コンセプトワークと戦略提案、そしてクリエイティブディレクションが主軸となる。ここはいつも同じ。