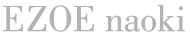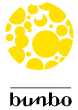tag:モノつくり
iPhone騒動。
2019.11.3それは突然やって来た。長く愛用のiPhone5SEが、まったく反応しなくなった。突然と言いながら予兆はあった。画面が乱れたり、フリーズしたり。いま思えば、断末魔の叫びだったか。さあ、困った。どれだけこのデバイスに頼っていたか、思い知らされるはめになる。
熊本川辺川。
2019.9.8名前はもちろん知っていた。伊達に釣り人はやっていない。球磨川の上流部、鮎で著名だが、釣り仲間たちからは本流でヤマメのライズがあると聞いていた。もっとも、基本遠征をしないので、他人事のように眺めていただけだった。それが突然我が事になりそうな展開。
雑味が残る。
2019.5.25珈琲とか、ワインとか、その領域では特に使われる表現。ボンヤリとした、なにか別の味が混ざっている感じ。味覚的異物感。望みの一色に染めきれないおぼろげな不満。あるいは、狙っている純度を保てないことを割り切れない薄いストレス。そんなニュアンスだろうか。
販路の幻想。
2019.4.26これまで、かなりの数の商品開発に携わってきた。食品から、家具、住宅、コスメ、ルアーまで、たくさんの分子との協働で、領域を超えた仕事を続けている。特に機会が増えたのは、10年程前から地域系のプロジェクトが比重が高まったことがきっかけだった。
相棒の一足。
2019.3.28いつ手に入れたか定かじゃない。10年はとっくに越えているはずだ。最初、アウトドア雑誌で見かけて興味を持った。それは使い古したよれよれの一品で、ソールの張り替えで甦る下りがあり、そのへたり具合がなんとも味があって、我が物としたくなった記憶がある。
僕の3.11。
2019.3.12福島へ行ってきた。あの忌まわしき震災から8年。農産物のブランディングに関するレクチャーが今回のお仕事。原発事故の風評被害という負の遺産を背負ったフクシマ。通常の方法論では、すぐに答は出ないかも知れないが、僕にできる復興支援はきっとこのあたり。
説得の行方。
2019.1.25プロデュースは編集であるという定義に加えて、プロデュースは説得業だと言うことがある。プロジェクトの局面局面で、他人の意識に働きかけ、考えを修正していただき、逡巡する気持ちを覚悟に変えていただく瞬間が必ず訪れる。推進のための重要なプロセス。
基準を作る。
2019.1.12もう随分前から腹の底に澱のように溜まっている不満がある。時折、掻き混ぜられて澱は舞い上がり、改めてどんよりした気分になる。それはスタンダードについてだ。基準と言い換えればいいだろうか。新しいビジョンやアイデアが、度々海の向こうからやって来る。
オンとオフの間。
2018.12.27年末年始はどんな我が身にも訪れる。年の瀬の雰囲気に押されて、つい来し方行く末をおもんばかったりする。今年もいろいろ考えたり、思い巡らせたけれど、そのひとつに公私の距離というのがある。オンとオフについては、ここ20年くらいで随分心境の変化があった。
不意の韓国へ。
2018.12.20扉はいつも突然に開く。ある日、某大学の先生からメールが届いた。曰く、淡路のプロジェクトについて書いた本の韓国語版が出ていて、それを読んだ韓国の方からレクチャーの打診があるという。以後は、直接連絡を取り合うようになった。日本語がご堪能で大助かり。
沈まない船。
2018.10.20これまで組織に所属したことは、1年強のサラリーマン生活のみ。以来、自由なような不自由なような、まあ気儘な人生。ただ、仕事でのお付き合いは組織のほうが断然多い。組織のなんたるかは、考えたくなくても考え続けるはめになる。良いところと悪いところ。
ルアー開発。
2018.10.7分野を特定しない仕事をしたくて、屋号をBunbo(分母)とした。これまで、多様な領域の分子とさまざまなプロジェクトを行ってきた。毎回ジャンルが違っても、コンセプトワークと戦略提案、そしてクリエイティブディレクションが主軸となる。ここはいつも同じ。
文脈の消失。
2018.8.17さまざまなプロジェクトが、時間を掛けて成就をめざす。発芽のようなアイデアの湧き出しがあって、発想は構想となって具現化が始まり、流れは太く強くなって加速する。しかし、一方では、その途上で計画の迷走や暴走が起こることがままある。なぜだろうか?
クワシマ。
2018.8.12クワシマからメッセが来た。唐突なのはいつも通り。クワシマの本名はコバヤシ。結婚のいきさつでなぜかそうなった。メッセはこうだ。イベントをするのでトークに出てくれ。そんな話だったので、ああいいよと取り敢えずのOKを出した。その名は城下町と市場。
真意を汲め。
2018.7.8提案の日々である。いや、これは我が身だけに限るまい。仕事と呼ばれる大半が、クライアント発の課題の解決にあるはずだ。勢い、ヒアリングは課題の確認に当てられるが、このときにほぼ勝負が決まる。クライアントの言葉を如何に聞くかがその分かれ道。