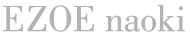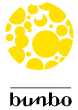tag:考察
狩猟の民。
2024.3.13生き方のタイプや人のキャラを言い分けるのに、狩猟型か農耕型という表現がある。前者は縄文的で、後者は弥生的といった線の引き方もあるだろう。僕自身は、縄文的な狩猟型の方に少なからぬ魅力を感じていて、若い頃はそんな人生を生きたいとボンヤリ思っていた。
脱YOU TUBE。
2024.2.24その時は突然やって来た。ずっとモニター上に出しっぱなしだったYOU TUBEのタブを閉じた。毎日毎日、実にさまざまな動画を観ていた。釣り、サッカー、料理、格闘技、お笑い、トーク、などなど。それはもう息抜きを超えて、膨大な時間を費やしていたと思う。
野暮こそ重罪。
2024.2.18貧乏は我慢できるけど、貧乏臭いのは許せないという言い方がある。とても腑に落ちる。誰もが心の奥底ではカッコ良くいたいとか、美しく生きたいと思っているはずで、ダサいのはいかにもイヤなのだ。僕の解釈では、ダサいと野暮はほぼ同義。野暮はいかんよ、野暮は。
無常について。
2024.2.6所詮一瞬だと思っている。いや、わが人生のことだ。薄っぺらい人生観の根底にそんな気分が確かに潜んでいる。それは今に始まったことではない。10代の終わりの混沌の中で、もがき苦しんだ挙げ句に掴んだ予感のような、諦観のようなもの。ただ、厭世感とは違う。
ジョグの翌日。
2024.1.25基本、1日おきに走っている。距離も3〜4kmだし、比較的ゆっくりなので、大したことはない。少しきつめの散歩と言ったところ。この秋には10年目に入るから、すっかり日常化した感じ。元来怠け者だから、ホントは楽したいが、コンディション維持には不可避なのだ。
当たるも八卦。
2024.1.13数字にからきし弱い。算数から数学に移行するあたりで、つまずいたことが最大の原因のような気もするが、生来の向き不向きも当然あると思う。いまもExcelを見ると軽い吐き気に襲われることがある。近ごろ話題の生成AIは、この弱点を補完してくれるに違いない。
役立たず。
2024.1.7これは何かの役に立つか否か。そんな視点で物事を眺めている人は多いだろう。それが余りに露骨になると、打算と蔑まれることもあるかも知れない。あるいは、無駄の排除。興味深いのは、何を無駄と思うかだ。この取捨選択が、人生を厚くもすれば薄くもする。
失敗の話。
2023.12.24あちこちでレクチャーなんぞをする。そこではほぼ必ず質疑応答の時間が用意される。話した内容を深掘りする、聞き手にも話し手にも意義ある時間だ。それはいいのだが、ごくたまに答え辛い質問も投げられる。曰く、成功した話じゃなくて、失敗談をぜひ聞きたい。
プロモに堕する。
2023.11.27ブランディングという考え方が広まって、もうしばらく経つ。全国各地の自治体にも、ブランド推進課といった地域のブランディングを掲げたセクションが生まれた。僕自身も言葉としてのブランディングは、比較的使う。もちろん、流行に乗りたいわけでは決してない。
要約の落し穴。
2023.11.18コピペの時代だ。原典からの引用は、文字が生まれて以降、古代からあっただろう。それが、デジタルが日常化した頃から激化した印象がある。限られた物書きにとどまらず、格段に増えた情報産業に関わる人たちが加速させ、一般ユーザーが罪の意識もなく拡散する。
江副の樹?
2023.11.12ここのえ低山部の、山の先輩たちに、そんな名前の木があると聞いたときは、もちろん冗談だと思った。いや本当にあったのだ。毎年、必ず春の新緑と秋の紅葉を楽しみに訪れる大分県庄内町男池。有名な湧水から少し歩いた先にこの木はある。見上げるほどの見事な大樹。
深更の思索。
2023.11.6早寝をすると必ず夜中に目が覚める。本当は朝まで前後不覚で熟睡したいのだが、加齢のせいかままならない。そうなればもう開き直って、PCを開いて、電子図書を読んだり、YOU TUBEを渉猟したりする。それは表層の快楽のようでもあるし、深い思索のようでもある。
ロジカル。
2023.10.31タイトルを「思考の整理」にするか迷った。まあ伝えたいことはほぼ同じ。プロデュースに関するレクチャーなんぞをしていると、たまに「なぜ、それを良いと思ったのか?」とか、「自身のアイデアに迷いはなかったのか?」といった問いを投げられることがある。
リセット力。
2023.10.1910年近くジョグを続けていて思うことがある。オリンピックに出るようなトップランナーたちは、同じ人間とは思えない異次元のレベルで、僕のような凡庸なジョガーを驚かすが、いったい何が優れているんだろうか。最近なんとなくわかってきた。それは回復力。
映画のように。
2023.10.13いやなに、仕事の仕方についてである。僕の会社ブンボは株式会社だが、経理作業を除けば基本ひとりでやっている。アシスタントがいたこともあったが、毎日出社してもらうようなことでもなかったし。結局、コピーライター時代のフリーランスと何ら変わっていない。